こんにちは、「ストーマライフなび」管理人のわるたーです。
今日は、オストメイトと障害者手帳というテーマでお話ししたいと思います。
手術を終えたばかりの頃は、毎日のストーマケアや体調管理で精一杯ですよね。私も退院直後は、社会福祉制度のことまで気が回りませんでした。 オストメイトになると障害者手帳を取得でき、自治体からのストーマ装具の補助や税金の控除、交通機関の割引など、さまざまな支援を受けることができます。
けれども、ある調査によると、オストメイトのうちおよそ1割前後の方が障害者手帳を取得しておらず、その割合は手術から間もない方が多いそうです。
そこで今回は、障害者手帳で受けられる主なサービスと取得までの流れについて、わかりやすくまとめてみました。
オストメイトは障害者手帳の対象になるの?
原則として、永久ストーマが造設された方が「身体障害者手帳」の対象になります。 一時的なストーマの場合は、治療の経過によって閉鎖されるため、対象外となることが多いです。
身体障害者手帳には、1級から7級までの等級があり、数字が小さいほど障がいの程度が重いとされています。
オストメイトの方は、身体の状態に応じて1級・3級・4級のいずれかに認定されます。
- 消化管または尿路のどちらか一方にストーマがある場合:4級
- 消化管と尿路の両方にストーマがある場合(ダブルストーマ):3級
- 他の障がいを併せ持つ場合:1級に認定されることもあります
※判定は医師の診断書や申請内容に基づいて行われるため、最終的な等級は自治体によって異なる場合があります。
手帳を取得すると、どんなサポートが受けられるの?
障害者手帳を取得すると、生活の中で役立つさまざまな支援を受けることができます。ストーマ装具の費用補助をはじめ、税金の控除や交通機関の割引など、知っておくと助かる制度がたくさんあります。 ここでは、主なサービス内容をわかりやすくまとめました。
日常生活用具(ストーマ装具)の給付
ストーマ装具を購入する際に、その費用の一部を補助してもらえる「日常生活用具給付券」を受けられるようになります。 給付金額には上限があり、自治体によって異なりますが、目安として
- 消化器系ストーマ装具:月8,800円前後
- 尿路系ストーマ装具:月12,000円前後
が多いようです。
原則として1割は自己負担となり、残りが市町村から給付されます。 申請はお住まいの市町村の障害福祉課で行います。
税金の控除・減免
- 所得税・住民税:障害者控除が適用され、税額が軽減されます。
- 自動車税・軽自動車税:オストメイト本人が運転する場合や、ご家族が運転して本人を同乗させる場合に、税の減免が受けられることがあります。
医療費の助成
医療費の自己負担分が軽減または免除される制度です。通院や薬代の負担が大きい方にとって、家計面で大きな助けになります。(対象となる等級や所得に制限があります。)
公共交通機関の割引
鉄道・バス・タクシー・航空機などの運賃が割引になります。通院や外出時の移動が多い方にとって、利用しやすい制度です。
施設利用料の減免
美術館、博物館、公園などの公共施設の入場料が割引または無料になる場合があります。民間のレジャー施設などでも、障害者割引が適用されるケースがあります。
※サービス内容は等級や自治体によって異なるため、詳しくはお住まい地域の福祉課や各施設に確認してください。
障害者手帳を取得するにはどうすればいい?
手帳の取得手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、流れを知っておくとスムーズに進められます。
以下が、障害者手帳を取得するまでの一般的な流れです。
- 市区町村役所で申請書類を受け取る お住まいの市町村役所の障害福祉課で、「身体障害者手帳交付申請書」と「身体障害者診断書・意見書(ぼうこう・直腸用)」をもらいます。
- 指定医に診断書を作成してもらう 障害認定ができる「指定医」に診断書を記入してもらいます。主治医が指定医でない場合は、窓口で紹介してもらうことができます。
- 書類を提出する 記入済みの申請書・診断書・写真(3cm×4cm)を市町村役所に提出します。
- 審査を経て手帳を受け取る 審査結果は、提出から1〜2か月ほどで届くのが一般的です。
※診断書の作成には時間がかかることもあるため、早めに主治医や窓口へ相談しておくと安心です。
おわりに
私はストーマを造設してから半年ほど経って、障害者手帳を取得しました。 ストーマ装具の交換やケア、通院など、オストメイトの生活には経済的な負担が少なくありません。 そんな中で、「障害者手帳」や日常生活用具給付券をはじめとする各種サービスは、生活を支えてくれる大切な制度だと感じています。
給付券や税の控除などの支援は、金銭的な助けになるだけでなく、「安心して暮らせる」という心の支えにもなります。
「自分も対象になるのかな?」と思ったら、気軽に役所や主治医に相談してみましょう。 制度を知り、うまく活用することが、“自分らしいストーマライフ”を送る第一歩になるはずです。

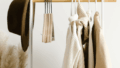
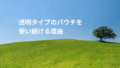
コメント